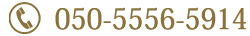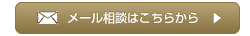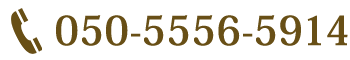1-1.国際裁判管轄とは
外国的要素を含む事件について,どこの国の裁判所が裁判を行う権限を有するか,という問題。
1-2.判例法理(条理説)
国際裁判管轄の公平的分配の見地から, 「当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により,条理に従い決定」 (条理説:最判平成8年6月24日)
1-3.国際相続事件における国際裁判管轄
国際相続事件においては,日本に一定の生活関連性が認められる場合に国際裁判管轄あり。
- ① 相続開始時点で日本に被相続人の住所がある場合
- ➁ 相続開始以前に日本に被相続人が居住する場合
- ➂ 相続人が日本に居住する場合
- ④ 相続財産が日本国内に存在する場合
1-4.立法による明文化
- 民事訴訟法改正(2011年):民訴法3条の2第1項以下に明文化
- 家事事件手続法3条の11および3条の13
- 遺産分割審判事件については合意管轄を認めるなど柔軟な規定あり。
2.準拠法決定のプロセス
- 法性決定の問題
通則法のルール(相続・婚姻・遺言・離婚・親子関係)かどうかを判断。
- (国際)相続は,被相続人の本国法による(法の適用に関する通則法36条)。
- 本国法決定
場所的不統一法国(アメリカなど),人的不統一国(インドなど),二重国籍等の場面で本国法をどのように決定するか。
- その他調整
反致,適応問題,公序等の調整。
3.地域的不統一法国に国籍を有する場合の本国法の決定
被相続人がアメリカ,イギリス,カナダ,オーストラリア,スペイン,メキシコ,中国などのように, 地域的不統一法国に国籍を有する場合における本国法の決定。
3-1.法適用通則法38条3項
「最も密接な関係がある地域の法」とは何か。
3-2.最も密接な関係の判断要素
被相続人の死亡時および過去の住所,常居所,家族の出身地,住所,常居所,居所などの客観的要素ばかりでなく, 被相続人の意思のような主観的要素も総合的に考慮して, いずれが被相続人とより密接な関係を有するかという観点から本国法を決定する。
4.相続における準拠法の決定(判例研究)
⑴ 相続開始
被相続人の死亡犠牲がなされる民事死や失踪宣告の場面で問題となる。
4-1-1.民事死
民事死とは,コモンローにおいては,重大な犯罪を犯した者(終身刑の宣告を受けた者や死刑の執行を待つ者)の権利能力を否定する制度。
相続準拠法が民事死を相続原因としている場合,法適用通則法42条の公序の適用が問題となる。 日本では,公序良俗に反し,適用を排除するとするのが通例(普遍的公序論)。
4-1-2.失踪宣告
本国法を原則(通則法6条)。例外的に日本に財産があるか,日本法によるべき法律関係がある場合のみ, 日本の裁判所が例外的に外国人に失踪宣告をすることが可能。
⑵ 相続財産の範囲
「亡Aの相続については,通則法36条により亡Aの本国法である日本法が準拠法となるから, どのような財産が亡Aの相続財産となるかについては相続準拠法である日本法によって定められる。 他方,ある財産ないし権利が相続財産となるためには,相続の客体性,被相続性を有することが必要であるところ, 相続の客体となりうるか否かは当該財産ないし権利の属性の問題であって,当該財産ないし権利に内在するものというべきであるから, 法律行為の成立および効力の問題として,通則法7条および8条が定める準拠法によって判断される。…… バンクオブハワイとの本件預金契約では,預金口座が2人以上の名前によって保有されている場合は, 預金口座はジョイント・テナント(合有所有者)として名義人に帰属しており, 所有者のいずれかが死亡した場合には,死亡した所有者の持分は自動的に生存所有者に移転するとされ, 預金口座が所在する地の法律によって規律される。…… バンクオブハワイとの本件預金契約では,預金口座は,預金口座が所在する地の法律により規律されるとの定めがあるから, 本件預金に適用される個別準拠法はハワイ州法である。…… 本件預金が相続の客体となりうるか否かを判断するについては, ハワイ州法において,ジョイント・アカウントをどのような制度としてハワイ州の法秩序全体が構成されているかに配慮しつつ検討すべきである。…… ハワイ州は,相続手続のほかに,死亡を原因とする財産移転の制度としてジョイント・テナシー(合有)の概念を持っているのであり,…… ジョイント・アカウントの死亡名義人の財産は,少なくとも死亡時においては, 制度として定められた生存名義人が所有するという以外の財産の移転を予定していないものといえるのであり, 他への一般的な移転可能性はないものと解されるから…… 共同相続人の死亡時においては,相続により移転することができず, 他への一般的な移転可能性もない財産としてハワイ州法が定めている。…… したがって,ジョイント・アカウントは,個別準拠法上, 相続の客体とならないものとして法秩序に組み込まれた制度というべきであり, 本件預金は相続の客体とはなりえないから,亡Aの相続財産を構成しない」
(平成26年7月8日判決・判タ1415号283頁)
⑶ 相続人の決定
「⑴渉外的な法律関係において,ある法律問題(本問題)を解決するために不可欠の前提問題が国際私法上本問題とは別個の法律関係を構成している場合, その前提問題の準拠法は,法廷地である我が国の国際私法により定めるべきである。
⑵渉外親子関係の成立の判断は,まず,嫡出親子関係の成立について,その準拠法を適用し, 嫡出親子関係が否定された場合には,嫡出以外の親子関係の成立についてその準拠法を適用して行うべきである。
⑶平成元年法律第27号による改正前の法令の下で,出生以外の事由により嫡出性を取得する場合の嫡出親子関係の成立の準拠法は, 嫡出性を取得する原因となるべき事実が完成した当時の母の夫の本国法である」として, 本問題の解決に不可欠な先決問題の準拠法決定方法については,本問題準拠法説ではなく, 法廷地国際私法説(相続と親子関係の成立は単位法律関係が異なるため, それぞれ別個に法廷地の国際私法が準拠法を決定するとする立場)を採ることを明確にした。(最判平成12年1月27日・判例タイムズ1024号172頁)
⑷ 相続財産の管理・清算
包括承継主義(ローマ法起源) VS 清算主義(ゲルマン法起源)
相続の過程の一つなので,国際私法上,相続準拠法により決定。
被相続人の本国法が英米法系諸国の法であるときは,日本では大抵「隠れた反致」が成立するため,日本法の適用によることが多い。 それ以外の場合,相続準拠法の趣旨を考慮して,法廷地の手続きを適用させ,日本の裁判所による代行を認め,遺産管理人を選任する必要がある。
たとえば,相続財産に関する債務過多となり,完済不能となった場合の相続財産の債務の清算は, 可能な限り,相続準拠法の定める方法・順位などを考慮して,その趣旨に合うように置き換える。
⑸ 遺産債務に対する責任,相続の承認・放棄
「通則法36条によれば,相続は被相続人の本国法によることとなる。 そこで,被相続人であるAの死亡時の本国法は何かを検討する。…… Aの外国人登録原票の国籍の欄には,朝鮮と記載されている。 しかし,証拠によれば,Aは1919年生まれであることが認められるところ, その当時は朝鮮半島において,大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とが存在する状況にはなかった(当裁判所に顕著な事実)。 また,証拠によれば,昭和17年生まれのY₁,昭和19年生まれのY₂,…はいずれも愛知県豊橋市が出生場所であることが認められる。 これらの事実によれば,朝鮮半島において,大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とが存在するに至る前から, Aが日本に居住していたことになる。 これらの事実に照らせば,Aの外国人原票の国籍の欄に『朝鮮』との記載があることをもって, Aの国籍が朝鮮民主主義人民共和国にあるとか,A死亡時の本国法が朝鮮民主主義人民共和国の法であると認めることはできない。 他方,大韓民国および朝鮮民主主義人民共和国の国籍に関する法律により, Aの国籍が大韓民国のみにあると認めるに足りる証拠もない。 以上の事情によれば,Aの死亡時および過去の住所,常居所,親族の住所,常居所,居所や本人の意思等をも考慮して, いずれの国の法をAの死亡時の本国法とすべきかを決定すべきである」
としたうえで,Aの死亡時の本国法は大韓民国の法であるとし,また,Y₄の相続放棄は効力を生じないとして, Xの請求を全部認容した。
(東京地裁平成23年6月7日判決・判タ1368号233頁)
⑹ 相続分,寄与分,遺留分
相続分・寄与分・遺留分は,相続準拠法によって決定する。 また,公序(通則法42条)により適用が排除されるかどうかは, 事案ごとに,当該規定の適用要件の解釈との関係で個別・具体的に決定する。
⑺ 相続財産の分割および移転
相続準拠法によって決定する。
⑻ 遺言の執行
「まず,本件の国際裁判管轄権であるが,遺言者の最後の住所地は東京都である…から,我が国に国際裁判管轄権がある。 次に,準拠法については,法例26条により遺言者の本国法によることになるが, インドには統一的な相続法が存在せず人的,宗教的な観点で適用する法律を異にするところ, 遺言者はゾロアスター教徒(パールシー)であって,相続につき同教徒に関する特別法が存在しないことから, インド相続法(Indian Succession Act)が適用になり,不動産については不動産の所在地法が適用される…(同法5条1項参照)。 また,動産(不動産以外の財産)については被相続人死亡時の所在地の国の法律が適用される(同法5条2項)。 そして,本件遺言の対象となるのは日本国内の不動産および日本に存在するかまたは日本に関係する預金,貯金,株券,社債等の動産(不動産以外の財産)である。 したがって,法例32条により反致が成立することになるので,本件は日本法によるべきことになる。 よって,本件申立てにつき,遺言執行者としては,本件遺言執行を行うことを受諾している会計士であるBを選任するのが相当である。」
(東京家裁平成13年9月17日)
⑼ 相続人不存在の財産
「被相続人に相続人があることが不分明であるかどうかの問題については, 法適用通則法36条により,被相続人の本国法を準拠法と解すべきであるが, 相続人のあることが不分明である場合に,相続財産をいかに管理し, 相続債権者等のために清算をいかに行うかおよび相続人の不存在が確定した場合に, 相続財産が何人に帰属するかの問題については通則法13条の規定の精神に従って, 管理財産の所在地法を準拠法と解するのが相当」
(東京家裁昭和41年9月26日・判タ218号285頁)
⑽ 特別縁故者への財産分与
「特別縁故者への財産分与については,相続財産の処分の問題であるから, 条理に基づき,相続財産の所在地法である日本法を適用すべき」
(名古屋家裁平成6年3月25日)
⑾ 相続代替制度
相続代替制度とは,ある人が自己の特定の財産を特定の受益者に相続の方法によらずに移転させることを意図して行う法律行為の効力を認める制度のこと。
例)
- 生命保険や個人年金についての受益者の指定
- 英米法系諸国の銀行で行われているジョイント・テナンシー(合有口座)やジョイント・アカウント(共同口座)
- 生存者間の信託など
「本件預金が亡きAの相続財産となるかについて検討する。… 亡きAの相続については,通則法36条により亡きAの本国法である日本法が準拠法となるから, どのような財産が亡きAの相続財産となるかについては相続準拠法である日本法によって定められる。 他方,ある財産ないし権利が相続財産となるためには,相続の客体性,被相続性を有することが必要であるところ, 相続の客体となり得るか否かは当該財産ないし権利の属性の問題であって,当該財産ないし権利に内在するものというべきであるから, 法律行為の成立および効力の問題として,通則法7条および8条が定める準拠法によって判断されることになる。 そして,バンク・オブ・ハワイとの本件預金契約では,預金口座は,預金口座が所在する地の法律により規律されるとの定めがあるから, 本件預金に適用される個別準拠法はハワイ州法である。 以上のとおり,本件預金が相続の客体となり得るか否かは,ハワイ州法によって判断すべきであり, 相続の客体となり得ない場合には,本件預金が亡きAの相続財産を構成することはないものというべきである。…… ハワイ州における相続手続は,統一遺産管理法典の定めによるものであり,…… 統一遺産管理法典には,死亡を原因とする財産移転の制度として,ジョイント・テナシ―(合有)と呼ばれる形態で財産が保有されている場合の財産移転が定められており, 不動産や有価証券,預金口座について,共同名義人の一人が死亡した場合には, 死亡名義人が有していた財産のすべてを生存名義人が絶対的,自動的に所有することになるのであり, その財産移転は相続ではなく,生存名義人が取得する権利(生存権)は遺言によって変更することができず,相続の対象ともならないから, 上記の相続手続きにおいて管理承継されることはない……したがって, ジョイント・アカウントは,個別準拠法上,相続の客体とならないものとして, 法秩序に組み込まれた制度であるというべきであり,本件預金は相続の客体とはなり得ないから, 亡きAの相続財産を構成しないものと解される。」
本判決は,ジョイント・アカウント預金について,その性質を分析し,相続財産性を否定した。 もっとも,日本法上,遺産分割や遺留分算定の際の考慮事項となるかは,なお残された問題である。 また,税法上は,みなし相続財産制度があり(相続税法3条以下), 本件預金が相続税の課税対象となったからといって,私法上,相続財産となるとは限らないとした。
(東京地裁平成26年7月8日)
5.遺言の成立および効力(通則法37条)
5-1.通則法37条
第37条1項 遺言の成立および効力は,その成立の当時における遺言者の本国法による。
第2項 遺言の取消しは,その当時における遺言者の本国法による。
5-2.通則法36条との関係性
- ⅰ 通則法37条1項は,遺言に固有な問題,すなわち遺言自体の成立および効力を規定したものであり, 遺言の実質的内容をなす行為の効力を規定したものではない。
- ⅱ 遺言の成立および効力とは,遺言に固有な問題,すなわち遺言自体の成立および効力の問題から, 方式の問題を除いたものをいう。方式の問題は特別法による。
5-3.遺言の方式
5-3-1.遺言の方式に関するハーグ国際条約(1960年)
「遺言の方式の準拠法に関する法律」により,選択的連結を採用。
5-3-2.選択的連結とは
以下のいずれかに適合するときは有効:
➀ 行為地法
② 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有していた国の法
➂ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有していた地の法
➃ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
⑤ 不動産に関する遺言については,その不動産の所在地法
5-4.判例の動向
5-4-1.遺言の成立および効力が問題となった事例
「本件遺言の方式は,行為地法であり住所地法でもある日本法上適法なものと認められる…また, 遺言の実質的な成立(遺言能力,意思表示の瑕疵の存否等)及び効力に関しては,… 遺言作成当時における遺言者の本国法がその準拠法となる。…… 本件においては,諸般の事情を考慮した上で,当事者と最も密接な関連を有すると認められる法域の法律を選択すべきものと解されるところ…… 亡トカレフはロシア共和国の出身であり,…本件における亡トカレフに関しては, ロシア共和国民法典をもってその本国法とするのが相当である。…… 本件における遺言者の本国法であるロシア共和国の国際私法規定は, 遺言を含めた相続関係全般…についてその準拠法を被相続人(遺言者)の住所地法と指定しているものと解されるのであって, 本件遺言の遺言者である亡トカレフの住所地は,死亡時及び遺言時いずれの時点においても日本国内であった以上, 本件遺言の成立(遺言能力等)及び効力(取消も含む)に関しては,…いわゆる反致が成立し, その準拠法は日本法であることになる。…… そこで,本件禁治産宣告の効力について判断する。国際法上, 特定の国家の国家機関による公権力の行使が可能なのは,その国家の領土主権の及ぶ範囲, すなわち自国領域内に限られるのが原則であり(属地的管轄権),自国民であっても, その者が他国の領域内に居住又は滞在している限り,その者は専ら当該居留地国の主権の下に服するのであって, 本国の国家は原則として当該国民に対して公権力を行使することができず, 特に居留地国の同意がある事項についてのみ例外的にその行使を許容されることがあり得るに過ぎないというべきである。 しかるに,禁治産宣告は,……公権力,特に広義の裁判権の行使たる国家行為であるから,…… 領事官がこれを他国の領土主権の下で自国民に対して行うことは原則として認められず, 特に当該接受国の同意がある場合に限り例外的に許容されるにすぎないと解するのが相当である。 そこで,日本国駐在の原告の領事官が禁治産宣告を行うことの可否につき, 接受国たる日本国の同意の有無が問題となるところ, 領事関係に関する日ソ両国の二国間条約である日ソ領事条約は, 「領事官は,その領事管轄区域内において,この部に定める職務を遂行する権利を有する。」との規定を置くとともに,… 右職務の内容を個別的かつ詳細に列挙している。 そして,右規定の体裁からすると,…各規定に列挙された事項は制限列挙であることが明らかであるところ,…… 右諸規定の中には禁治産宣告に関する規定は存在せず,むしろ,… 領事官が接受国の裁判所等に対して後見人を推薦することを認めるに止まっている。… 同条約は,禁治産宣告はもとより,これに付随する後見人の選任についても, その権限を領事官に対して許容してはおらず,これを列挙事項から除外しているものと解するのが相当である。…… 日本の国内法上も禁治産宣告の権限を領事官に委ねることを定めた法令は存在せず, 同条約の趣旨も,…禁治産宣告の権限を領事官の職務権限から除外しているものと解される……そうすると, 日本国駐在の原告総領事には日本国内において在日ソ連人に対し禁治産宣告を行う権限は認められていないものと解するのが相当であるから, 本件禁治産宣告は,そもそも権限を欠くものとして,その効力を有しないものと解される。」
(東京地裁平成3年12月20日)
5-4-2.遺言執行者の選任に関する事例
「本件申立ての要旨である遺言執行者の選任は,遺言の成立あるいは効力の問題ではなく, 遺言によって発生すべき相続財産の移転という実質的法律関係,すなわち相続に関する問題といえる。…… ところで,法例25条(現36条)によると,相続は被相続人の本国法によるべきところ, 英法においては,相続に関する国際私法の原則として不動産物権については所在地法, 人的財産すなわち不動産以外の権利については被相続人の住所地法によるという原則が確立されているという。… そして,被相続人の住所がいずれにあるかは英法上の住所概念(domicile)によるべきものと解されるところ,… 被相続人は…日本を終生の地とする意思であったことが推認できるから, 被相続人は我が国に英法上の住所(domicile)を有していたものと認められる。 しかるときは,日本に所在する被相続人に属する不動産以外の権利に関する遺言執行の準拠法として, 被相続人の本国法によるべきその本国法によれば住所地法たる日本の法律のよるとしている場合であるから… 法例29条(現41条:反致)により日本民法を適用すべきものと判断される。 以上の次第であるから,本件遺言書については日本民法に基づき遺言執行者を選任すべき…こととし, 主文のとおり審判する。」
(東京家裁昭和45年3月31日)
5-4-3.遺言の検認に関する事例
「…遺言の成立及び効力はその成立の当時における遺言者の本国法によることとされ, また遺言の方式の準拠法に関する(法例)によると遺言はその方式が, 行為地法,遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律, 遺言者がその当時住所又は常居所を有した地の法律,不動産所在地法のいずれか一に適合するときは方式に関し有効である, と規定されている。本件遺言者は…フランス国籍を有していたので, その方式を同国民法によって検討する。…… 本件遺言は…フランス民法上の公正証書遺言の方式に関し有効であるということができる。…… そして,遺言の執行前に相続開始地の一審裁判所に遺言書を提出して開封し公証人に寄託すべきことを規定するフランス民法一〇〇七条は 自筆遺言書又は秘密方式の遺言に限り義務付けられており, 公正証書遺言についてはこのような手続きは存在しない。 これと類似した手続きとして遺言書の検認手続を義務付けている日本民法一〇〇四条一項も同様に… 公正証書遺言には適用を解除されている。 そうすると,本件遺言書は,公正証書の方式によるものであるから, フランス民法によっても,日本民法によってもとものその執行開始前になすべき効力発生要件としての家庭裁判所による検認手続は必要としないことは明らかである。」
(神戸家裁昭和57年7月15日)