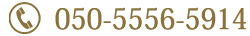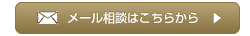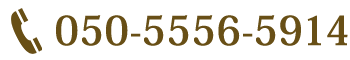Q
国際相続とは何ですか?
A
国際相続とは、相続関係を構成する何らかの要素が外国に関連する相続をいいます。例えば、相続人や被相続人、または相続財産が複数の国に関わる場合などです。
Q
相続が「国際相続」となるのはどのような場合ですか?
A
被相続人が外国に資産を保有していたり、相続人が海外在住・外国籍である場合などです。1つでも国外要素があれば国際相続と考えられます。
Q
国際相続は珍しいことでしょうか?
A
近年は珍しくありません。人,物,お金のボーダレス化を背景に,急激に国際化が進んでいることが背景にあります。海外赴任や投資、不動産購入などで、複数国に財産や家族のつながりを持つ人も多くなっています。
Q
相続における「準拠法」とはどういう意味ですか?
A
準拠法とは当事者となる人の国籍,住所,目的物の所在地など地域的要素が複数国にかかわる場合,「どの国の法律を適用して処理するか」を決めるルールです。日本では,この準拠法を定める法律を『法の適用を定めに関する通則法』として規定しています。国際相続では国ごとにルールが異なるため重要です。
Q
日本の法律では、相続に際して一般的にどの法律が適用されますか?
A
日本の国際私法では、相続財産の種類や所在地によって区別することなく,一律,被相続人の「本国法」が準拠法とされます(相続統一主義)。日本で問題となるからといって,民法ですべて解決できるわけではない点に留意が必要です。
Q
不動産にはどのような法律が適用されますか?
A
原則として不動産の所在地の法律が適用されます。例えばアメリカにある不動産はアメリカ法で処理されます。
Q
日本の「相続の一体性」とは何ですか?
A
日本法では原則、財産の種類や所在場所に関わらず「まとめて一体的に」処理する考え方です(いわゆる相続統一主義)。ただし実務では、現地の法制度の影響を受ける(例えば,アメリカに預貯金や不動産を所有している場合など)ことが多いです。
Q
一部の国で採用されている「相続分割主義」とは何ですか?
A
国によっては「その国にある財産だけを、その国の法律で処理する」という考え方があります。これを相続分割主義と呼びます。アメリカ,イギリスといった英米法系諸国,フランス,中国などが採用しています。
Q
日本の「遺留分」(強制相続)制度は海外にもありますか?
A
多くの国に似た制度があります。フランスやドイツなど大陸法系の国には強い遺留分制度があり、米国などのコモンロー系では弱いか,もしくは存在しません。
Q
米国の相続手続きは何と呼ばれていますか?
A
米国では「プロベート(probate)」と呼ばれ、裁判所を通じた手続きが必要です。
Q
外国人配偶者は日本で相続できますか?
A
日本国籍を有する者の配偶者は外国人であっても相続権を有し,日本で相続ができます。ただし相続税の扱いには制限や特例がある場合があります。
Q
海外に住んでいる相続人も相続できますか?
A
可能です。ただし現地に生活の本拠を有しており,日本への住民登録がない,日本国籍を有しない場合など,円滑な相続手続が困難になる場合には,弁護士など専門家を通じて進めるのが一般的です。
Q
日本の遺言は海外でも有効ですか?
A
国によって有効とされる遺言要式が異なるため注意が必要です。海外に相続対象となる財産がある場合には,現地の要式に沿った遺言を別途用意することが望まれます。
Q
外国の遺言は日本でも有効ですか?
A
日本では認められない遺言方式であっても,遺言者の本国法や遺言作成地の法で認められる方式で作成されていれば日本でも有効となります。日本は「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」に加盟しており,条件を満たせば外国方式の遺言も有効と認められます。
Q
資産がある国ごとに遺言書を作成する必要がありますか?
A
日本は相続財産の所在地に関係なく,被相続人の本国法を適用する相続統一主義を採用しており,必ずしも国ごとに遺言が必要なわけではありません。ただし,国ごとの要式に沿った遺言を用意しておくことで手続き上の混乱を防ぐことができます。
Q
海外不動産の所有権は相続でどのように移転しますか?
A
原則として現地法に従います。不動産登記や裁判所の承認が必要な国もあります。
Q
海外の銀行口座はどのように相続されますか?
A
現地の銀行規定や法律に従います。相続人の証明書類や日本の戸籍が求められることが一般的です。
Q
相続財産はどのように特定されるのですか?
A
遺言執行者が預金通帳、不動産登記簿、証券口座、税務申告書などを調査し、日本・海外双方の資産を特定します。
Q
外国の銀行は日本の書類を受け付けますか?
A
そのままでは受け付けない場合もあります。翻訳、公証、アポスティーユ(ハーグ条約に基づく外務省証明)などが必要となるケースがあります。
Q
日本の戸籍は海外でも有効ですか?
A
有効ですが,多くの場合は翻訳や公証が別途必要になります。
Q
国外財産は日本の相続税の対象になりますか?
A
被相続人や相続人が日本に住所を有している場合、国外財産も課税対象になります。
Q
外国でも相続税は課せられますか?
A
国により異なります。米国やフランスには相続税があり、中国,シンガポール,インドネシア等には現時点では存在しません。
Q
二重課税は回避できますか?
A
相続税条約や外国税額控除を使うことで回避可能です。
Q
相続税条約とは何ですか?
A
日本と特定の国との間で締結された、相続税や贈与税に関する二重課税を防ぐための条約です。たとえば,日米相続税条約などが有名です。
Q
生前贈与によって国際相続税を軽減することはできますか?
A
一定の効果があります。ただし各国の贈与税制度にも注意が必要です。
Q
海外にいる相続人と連絡が取れない場合はどうなるのでしょうか?
A
失踪宣告や不在者財産管理人を選任し、代理で手続きを進めることが可能です。
Q
外国人弁護士を雇う必要はありますか?
A
海外不動産や口座の手続きがある場合、現地弁護士の協力が不可欠なケースがあります。
Q
日本の弁護士だけで全てを処理できますか?
A
国内部分は可能ですが、海外部分は現地専門家との連携が必要です。
Q
国際相続手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?
A
国内相続より長く、数か月から数年かかることがあります。とりわけ海外不動産や銀行口座の処理には煩雑な手続きを要し,時間がかかることを念頭においた方がよいでしょう。
Q
手続きにはどれくらいの費用がかかりますか?
A
ケースによって異なります。翻訳、公証、現地弁護士費用などが追加で発生する点が特徴です。
Q
日本人がアメリカで亡くなった場合、相続はどのように扱われますか?
A
被相続人が日本人である場合,原則として,準拠法である日本法に基づき相続手続がなされますが,仮にアメリカにも資産がある場合,原則として裁判所の関与のもとでの相続手続(プロベート)が別途必要となります。また,日本でも相続税などの税務申告などを行います。
Q
外国人が日本で死亡した場合はどうなりますか?
A
原則として被相続人の本国法に従いますが,相続の対象が不動産や銀行口座預金である場合,実務上は当該財産の所在地法を適用することが多くあります。たとえば,日本に所在する不動産は日本法で処理されます。
Q
海外に不動産を所有している場合に相続はどのようになされますか?
A
不動産は所在国の法律に基づき相続手続を踏む必要があります。そのため,日本での相続協議(遺産分割協議)だけでは不動産の所有権を移転することはできません。
Q
日本人が海外の銀行口座を持っている場合はどうなりますか?
A
口座を作成した銀行の本店所在地の規則に従い、書類を提出して相続手続きを進める必要があります。
Q
外国人配偶者は日本でどのように相続するのですか?
A
他の相続人と同じように法定相続分を得られます。ただし相続税の非課税枠は居住要件によって異なります。
Q
海外の相続人が異なる相続分を主張する場合はどうなりますか?
A
調停や裁判で調整が必要です。複数国の法制度の違いにより,裁判が予想以上に長期化する可能性があります。
Q
外国人相続人は日本において「遺留分」を受け取る権利がありますか?
A
相続人であれば国籍に関係なく日本の遺留分制度の対象になります。
Q
相続人が海外で訴訟を起こした場合はどうなりますか?
A
国際裁判管轄の問題が生じます。場合によっては日本と海外で二重に手続きが進むこともあります。
Q
異なる国にいる相続人との話し合いはどのように行われますか?
A
オンライン会議や、現地代理人を通じて行うのが一般的です。
Q
相続人が海外での協力を拒否した場合はどうなるのでしょうか?
A
協力が得られない場合は、調停や裁判を通じて解決を図るしかありません。
Q
どのような準備が効果的ですか?
A
遺言の作成、財産リストの整理、弁護士といった相続を扱う専門家への事前相談が最も有効です。
Q
海外の財産を日本における相続人間の遺産分割協議で分割することはできますか?
A
協議自体は有効ですが、実際の所有権移転のための登記手続等は財産所在地の法律に従って行う必要があります。
Q
日本の家庭裁判所はいわゆる国際相続に係る案件を扱うことができますか?
A
国内財産については扱うことができますが、海外不動産については管轄外です。
Q
国際相続を扱う弁護士はどのように選べばいいですか?
A
国際案件の経験や、外国の専門家ネットワークを持つ事務所を選ぶのが望ましいです。
Q
翻訳と通訳は必要ですか?
A
戸籍や遺産分割に関する協議書には翻訳が求められます。また、国際協議では通訳も重要です。
Q
国際相続は弁護士なしでもできますか?
A
可能です。もっとも実際上は非常に複雑な手続きと時間を要することが想定されますので、弁護士といった専門家に依頼するのが良いでしょう。
Q
相続が始まる前に専門家に相談した方が良いでしょうか?
A
国際相続の手続きは複雑多岐な事項にわたるため,事前に専門家に相談のうえ,生前のうちに遺言書の作成や財産整理をきちんと準備しておくことで,紛争の予防や相続手続きをより円滑に進めることができます。
Q
国内相続と国際相続の最大の違いは何ですか?
A
相続手続が複数国にまたがって処理する必要がある点です。法律・税制・言語・慣習の違いが大きなハードルとなり,手続が長期化する可能性があります。
Q
外国の不動産は必ず紛争を引き起こすのでしょうか?
A
必ずしもそうではありません。もっとも,現地における相続手続や不動産の評価額算定の違い等から紛争に発展しやすいといえるでしょう。
Q
国際相続において最も重要なことは何ですか?
A
「事前の準備」と「専門家の活用」です。事前に財産目録を作成し,当該財産の所在する国の要式に沿った遺言書を作成すると同時に、国際相続について十分に経験のある弁護士・税理士を関与させることが重要といえるでしょう。